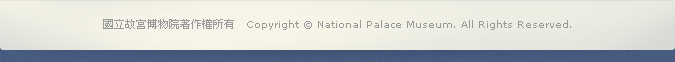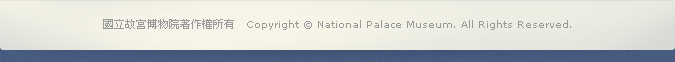|
|
|
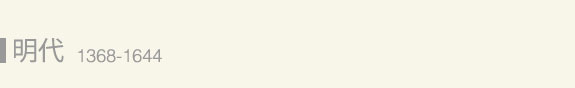 |
|
| |
陶磁器の焼造は明代における国家の大事でした。明代初期、浙江省の龍泉窯と江西景徳鎮が陶磁器産業の中心として発展し、焼成された陶磁器は中国全国各地に広まったばかりでなく、海外市場にも広く伝えられ、同時に皇室の御用達品として宮中に納められていました。
明代初期に御用窯が景徳鎮に設立され、その後五百年に及ぶ景徳鎮官窯の規模と制度が確立されました。この頃の官窯は、政府が直接見本を提供し、監督を遣わしていたため、御用窯は一定の制度の下で品質や生産量が常に管理され、完成品も選別を経て直接宮廷に送られ、皇室と役所に供されました。明代の官窯は、永楽年間から磁器に皇帝の年号を入れるようになり、後の各時期における官窯の決まった形式となりました。永宣の青花、成化の豆彩、嘉万の五彩などは、明代の官窯が収めた比類なき最高の成果と言えるでしょう。
当時、景徳鎮以外の一般の民窯でも磁器を生産していました。官窯と民窯は品質、生産量、窯炉の形式と規模、工房の運営形式、ひいては作品のスタイルに至るまで大きく異なっていました。
明代晩期に至ると、政治や経済状況の変化により、社会に多元的な価値観が生まれ、官窯には優れた原料があったものの、管理にゆるみが生じ、技術にも秩序がなく、これに取って代わるように台頭したのが民窯でした。
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|